過保護な親の特徴と甘やかされて育った子の行く末
・もしかしたら過保護かな?と心配になる時がある
・過保護と過干渉の違いを知りたい!
・どんな行動が過保護に当たるのかを知りたい
みたいなお気持ちのある方に向けて、過保護な親の特徴と、そんな親御さんに甘やかされて育った子どもの将来的に起きる事についてお伝えします。
中高生ママ専門の子育てコーチとして、沢山のご家庭の問題をお聞きしてましたが、少子化が進む今の日本では、特に教育熱心なご家庭において、過保護な子育てになっていることが多いなぁと感じています。
理由は、勉強することや同級生達から遅れをとらないこと(=皆よりも優秀であること)を優先しているために、親は良かれと思って先回りしてお膳立てしている方が多いからです。
実は、過保護な親に育てられた子は、特に思春期以降は以下のような特徴がみられます。
1)親のせいにする
2)自分で決められない
3)打たれ弱くなる
子どもの為を思う親の気持ちとはうらはらに、結果として、子どもに悪影響を与えてしまいます、、、
今日はどの行動が過保護に当たるか、がわかりやすいように、過保護な親御さんがとりがちな行動やその理由について解説しています。
もくじ
過保護とは?過干渉との違い
過保護とは、子どものことを必要以上に甘やかしたり、要望を叶え過ぎてしまったりすることです。
今の日本は少子化が問題にもなっていますが、昔に比べて親が一人の子どもに関わる密度が濃いために、どうしても過剰に保護してしまうことが多くなっているのでしょう。
ですので、特に一人っ子の親御さんは、過保護になりやすいという訳です。
また、過保護と似ている言葉として「過干渉」があります。
過干渉は、「子どもが望んでいないこと」を、良かれと思って、親がやり過ぎてしまうこと。
例えば、(本人が望んでないのに)塾を勝手に決めてきたり、テスト勉強のスケジュール管理をしたり、みたいな感じです。(詳しくはコチラを)
過保護は、「子どもが望んでいること」を、良かれと思って、親がやり過ぎてしまうこと。
例えば、(自力で通える距離なのに)塾や駅までの送り迎えなどです。
つまり、どちらも子どものことを心配して「良かれと思って、親がやり過ぎてしまうこと」ですが、一般的には、過保護よりも過干渉の方が毒性が強くなり、毒親の特徴と言われています。
▼過干渉かどうか心配な方に▼
⇒過干渉な親チェックリストどこからが毒親
過保護な親になりやすい5つのタイプ
では、そんな「過保護になりやすい親」の5つのタイプ(性格)をご紹介します。
基本、女性が(母親)が多いですが、心配性の男性(父親)もなりやすいです。
- 心配性
子どものことが心配でたまらず、常に子どものことが頭にある。また子どもの可能性を信じることが出来ず、ドリームキラーにもなりやすい。
- せっかち
子どもにやらせるよりも、自分がやる方が早いので、ついつい自分で何でもやってしまうタイプ。また、子どもが困る前に、親が何とかしてしまうことが日常化しているので、自分のアタマで考える力が育たない。
- めんどくさがり屋、か・ら・の段取り上手
過去に、子どもがらみでの「めんどくさい出来事(例:学校からの呼び出しなど)」があったために、再度めんどくさい事態を引き起こさないように、段取りをするのが習慣化している - 完璧志向
常に周りと比較し、平均点以上や最高の子育てを目指している。真面目な優等生タイプが多く、常に「正しい」かどうかが判断基準になっている
- 世話焼き気質(承認欲求が強い)
人から感謝されると嬉しいので、余計なお世話が多くなる。「余計なお世話」であることは、自分でもうすうす気づいてはいるが、このタイプの方は「これは自分の性分だ」と何故か割り切っていて、世話焼きを辞めない人多し。
過保護な親の特徴
過保護な親御さんは、基本視野が狭くなっていて、自分の考えだけに囚われがちです。
ですので、子どものために自分が良いと思ったことは(正しいことだと思い込んで)ずっとやり続けてしまうのですよね…
また、自分自身も過保護な親に育てられている(=世代間で連鎖している)場合も多いです。
では、ここで一つ質問です。
もしも飢えた人がいたとしたら、あなたは
(1)魚を釣ってあげますか?
(2)それとも魚の釣り方を教えてあげますか?
きっとご存じの方も多いこの話。
実は「子育ては、子どもの成長の段階によって親も変わる必要があること」を教えてくれる、とても秀逸なたとえ話なのです。
子どもが小さなうちは、もちろん(1)魚を釣ってあげることが必要です。
ただ、子どもが成長するに従って、だんだん(2)魚の釣り方を教えてあげる段階へとスタンスを変化させていくことが大事です。
ですが、過保護な親御さんは、子どものためにずっと魚を釣ってあげるステージにいて、「この子は自分が面倒見てあげないとダメだ」とばかりに、過剰に保護し続けてしまっています。
例えば、「金持ちの放蕩息子」なんて言葉がありますが、これは経済力のある親がずっと子どもを甘やかし保護し続けるために、自分の力で生きていく力が育たず放蕩息子になってしまうのでしょう。
子どもが、自分で魚を釣る方法をマスターして、一人で生きる力を身に付けるためには、親は釣り方を教えてあげた後に、失敗も含め試行錯誤する期間を黙って見守ってあげること(←見守る期間でココ大事)が重要です。
「失敗するとわかっていてもさせる勇気」をどこかの段階で持たないことには、大切なわが子の「生きる力」を育てることが出来ないのです。

自分一人で生きていけるように
「生きる力」を育てたい!
***
そのためには
魚の釣り方を教えた後
失敗すると分かっていても
一人でさせてみる勇気が必要です
過保護な親の5つの行動とその理由

失敗しないように
頑張り続けなさい
あなたのためなのよ~~
ヘリコプターペアレントという言葉をご存じでしょうか?
ヘリコプターペアレントとは
引用元:weblio辞書ヘリコプターペアレント
自分の子供に対し過保護なあまり、他人に迷惑をかける「モンスター・ペアレント」の中でも、特に、子供に付きまとい、子供とその周囲の人間を監視するなどの行為が目立つ親のこと。 ヘリコプターのような親が子供の頭上を旋回するイメージからつけられた呼称である。
もともとアメリカで広まった言葉ですが、過保護な親をヘリコプターに例えた「コミカルさ」のためか、最近は日本でも多く聞かれるようになりました。
では、ヘリコプターのように子どもの上空を旋回しながら子育てしている、過保護な親御さんがとる行動を5つと、その理由をお伝えします。
- 身の回りのことは全部やってあげる
高校生になっても、勉強以外のことは全部親がやってあげているご家庭は、ぶっちゃけ進学校のご家庭で多く見られます。
(例、翌日の持ち物や洋服の準備、部屋の片づけ、プリント類のファイリング、お小遣いの管理、魚の小骨とり、友達への連絡など)
生活全般とまではいかなくても「今日は雨だから、傘持っていきなさい」「お弁当はちゃんと持った?」(→毎日母が鞄に入れてあげている場合も有り)など、子どもが外出先で困らないように、毎回声をかけをしたり、持ち物を準備してあげているお母さんは多いのではないでしょうか?
(理由:困ったらかわいそうだから、テスト前のこの時期に風邪をひいたら大変だから。実際は、失敗させたくないなど) - 欲しがるものは全て買い与える
富裕層家庭のお子さんや、孫に甘い祖父母がいらっしゃるご家庭に多い特徴です。
(理由:かわいいから。かわいそうだから。嫌われたくないから。つまり親や祖父母の自己中な気持ちでやってしまっていて、子どもの為になっていない) - 外出時など一緒に行動する(送り迎え)
心配症の度が過ぎて、自力で行ける距離なのに、学校や駅や塾の送り迎えをしている
(理由:夜だから、雨が降って濡れたらかわいそうだから。実際は、塾に遅れないように行かせたいなど) - 本人が困る前に先回りしてお膳立てする
失敗させるのが嫌なので、例えば、宿題のプリントを学校に忘れてしまった時にママ友に頼んで写メを送ってもらったり、友達と同じ塾に行かせたくて、「一緒に行こう」と声をかけてくれるようにママ友からそのお子さんへ頼んでいたり。
とにかく子どもが困らないように、失敗させないようにしている。
(理由:失敗させたくないから。子どもが失敗する姿を見たくないなど) - 本人の問題に介入して解決しようする
習い事や部活など、何に入る or 入らない、休む or 休まない(休ませない)、辞める or 辞めない、などの問題に、親が必要以上に悩み、関与している
(理由:家でゲームばかりになるよりも健全な趣味を持った方がよい、子どもは身体を動かした方がよい、始めたことを途中で辞めてはダメだからなど。実際は、家で子どもがダラダラする姿を見たくないなど)
過保護な親に育てられた子の特徴と行く末
では、過保護に育てられた子どもはどんな特徴があるのでしょうか?
今回3つの特徴をご紹介しますが、もしも今、こういった現象が確認できるようでしたら、過保護を卒業するタイミングです!
今日からの言動を見直してみましょう。
1)親のせいにする
過保護に育てられた子は、何かあると親のせい(人のせい)にすることが多くなります。
それは、親が何でも先に決めていて(良かれと思って)、自分でやりたいこと、やりたくないことを選択していないからです。
実は、中高生ママ達から私へのご相談で、とても多いのが「朝起きない子ども」のお悩みです。
特に、母は何度も声をかけているのに「朝起こしてくれないから遅刻した。どうして起こしてくれなかったの!」と、親のせいにする子がとても多いのです。
「遅刻するくらいなら休む」というタイプの子も多いので、「学校を休まれては大変だから」と毎朝ストレスを抱えながらも、子どもを起こし続けておられるんですよね…
本来、「朝起きること」は子ども自身の問題で、ぶっちゃけ、小学生でも出来る事。
なのに、なぜか「朝起こすこと」(=学校に行かせること)がお母さんの仕事になってしまっているために、自分の遅刻を親のせいにする子になってしまっています。
自分の問題を自分で解決できる子に。
人のせいにしない子に育てていきましょう。

お母さんが子ども以上に
悩まないようにしましょう
2)自分で決められない
親に必要以上に保護され続けると、自分で決められない子に育ちます。
どうしてかというと、たいていのことは親が決めてきたので、圧倒的に自分で決めた経験が少ないのです。
また(指示命令の多い)親の言う通りにしておけば、失敗することは少なくなりますから、ある意味ラクなんですよね…
自分で考えることを放棄して、親に依存している状態です。(親も子どもに依存すると共依存となり非常に抜け出しにくい)
ですので、例えば、高校生になっても
子「今日は部活に行った方がいいかな?」
子「自分はどの大学に行けばよいの?」
など、一人で決めることが出来ずに、常に親や友達の意見を伺うようになったりします。
これは、一見「親の言う事を聞く良い子」でもあるので、育てやすいと感じるかもしれませんが、子育てコーチとしては、将来が非常に心配です。
▼参考記事▼
⇒共依存の親子の特徴とは?断ち切って自立に向かう為の5つの方法
3)打たれ弱い
失敗させないようにと、親が先回りして、過保護に育ててしまうと、どうしても打たれ弱い子になります。
どうしてかというと、親が何でもやってくれていたために生活力が備わっていませんし、失敗経験も、そこから立ち直った経験も少ないからです。
例えば、学生時代真面目で優秀だった子が、社会に出て、たった一度の失敗をきっかけに引きこもってしまったという話を聞いたりしませんか?
こういう話を聞くと、私は、過保護に育てる危険性を強く感じるのです。
私たち親は先回りの育児をしないようにし、特に学生のうちは、沢山チャレンジして失敗する経験を(モチロン成功体験も!)させてあげることがよいと考えています。

特に、「かわいそうだから」という気持ちが湧いてきた時は要注意です。
「可愛そうだから→私が何か出来ることないかしら?」というマインドになり、過保護になりやすいですから。
過保護な親にならない為に
では、過保護な親にならない為に、私たちは何に気を付けたらよいのでしょうか?
それは、「親が子どもの問題に介入しないこと」←これが非常に大切です!
例えば「子どもの喧嘩に親が出るな」とはよく言われます。
親は子どもの貴重な成長のチャンスを邪魔してはイケナイという意味で言われている言葉だと認識しています。
ですが、過保護や親の場合は、子どもの喧嘩の途中でしゃしゃり出てしまい、子どもの問題を親が解決してしまいます。
「うちの子は、口下手だから負けてしまう…。かわいそう。だから私が…」みたいな感じで、黙っていられなくなり、緊急出動してしまうんですよね…
こんな風に、親が子どもの問題に介入し続けると、「コミュニケーション能力」を始め、自主性や主体性など、笑顔で自立するために必要な力が育ちません。
【子ども同士の喧嘩の場合】
❶自分の意見をちゃんと相手に話すこと
❷喧嘩した後は、自分で後始末すること
などが経験できるために、子どもの社会性を育てる上でとても貴重な機会ですから、心のママに動いてしまって、子どもの成長の機会を奪わないようにしたいものです。
そして、この対策として、子育てコーチの私からオススメの行動があります。
それは、どうすればよいかを迷った時に、Q.「これは誰の問題?」と自問してみる事です。
たいていの場合、「子どもの問題」を解決しようとお母さんが悩み過ぎていることが原因だったりするからです。
ですので、子どもの問題に介入しようとしていたことに気付いた後は、心の中で「この子は大丈夫。自分の問題を自分で解決する力を持っている!」と信じて、見守るようにしていくと、過保護や過干渉からも卒業できます。
まだ社会に出る前の中学生~高校生~大学生の時期は、自分の力で魚を釣れるようになって自立しよう!と本人も試行錯誤している時期です。
そんなわが子のことを、温かい目で見守って、精神的に自立した親子関係になれますように。
番外編:甘やかすと甘えさせるの違い
過保護は甘やかすことでもありますので、もしかしたら、この記事を読んで「今日から甘やかさない!」と極端なやり方に転じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
実は、甘やかすのは良くありませんが、甘えさせること(子どもの心理的な欲求を受け入れる事)はとても大事です。
特に、しつけやルールが非常に厳しいお宅で、親からの愛情に飢えているような場合、甘えさせてもらないことが原因で荒れているお子さんも多いですので、もしよかったら以下の記事を参考になさって下さいね。
▼甘やかすと甘えさせるの違い▼
⇒【男の子を甘やかす親の心理】甘えさせて自立する子を育てよう
▼もしかしたら愛情不足?サインを知りたい方に▼
⇒【小・中・高校生別】愛情不足の子どもの特徴とサイン
▼(PR)勉強しない!ゲームばっかり!にお悩みママに
\どちらも無料/
❶メール(文字)で学びたい方に⇒7日間メールセミナー(登録無料)
❷(New!)動画で学びたい方に⇒7日間【動画】セミナー(登録無料)
この記事を書いた人(監修者)
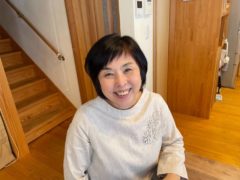
長野県松本市在住
中高生ママ専門の子育てコーチとして、悩める母専門のコーチングセッションを行う。
【経歴】
・コーチングオフィス ままはぐ代表
・ICA国際コーチ協会認定 ポテンシャルコーチ
・セッショントータル4,500時間以上を実施
・24歳(社会人)と21歳(大4)2人の息子を持つ母親
・京都大学にて教授秘書歴7年
New! オンラインサロン「母テラス」

月額3900円で
ブレない子育て軸を手に入れませんか?
2024年1月~「見守る子育て」のオンラインサロンができました\(^o^)/
❶月替りで有料動画 ❷個別サポート先行案内 ❸ランチ会も! ❹LINEでカンタン♪ ❺匿名で参加できる ❻コツコツ行動→なりたい自分に速やかに成長❼zoomセミナー(お悩み回答室)など。
動画で学べて(インプット)、チャット欄で毎日アウトプットできるから、1日でも早く!「見守る母」になりたい方に超オススメ。
子育てこんなに頑張っているのに!!どうしても毒を吐きたい時は「毒吐き→浄化ルーム」へどうぞ。
3日くらいしたら私がそっと「早く笑顔になりますように☆」という気持ちを込めて、その投稿をそっと消去しています。(始まってすぐに人気のお部屋になっています)
お知らせ
ただいま、わかばやしが直接サポートするコースは満席になっており、お申込みをストップしています。
空きが出ましたらライン@やメルマガにてお知らせさせていただきます。(2023年2月中旬に3月生さんを若干名、募集予定です)
\登録無料/
▼ライン公式アカウント(←週3でブログ更新のご案内があなたのスマホに届きます♪)

週3回の配信
▼7日間無料メールセミナー(←こじらせていた私自身の話)
毎週(月)朝に配信
▼YouTube わかばやしゆかこ「見守る子育て塾」週2更新♪
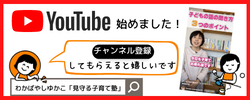
YouTube週2回更新♪
チャンネル登録していただけると
嬉しいです~~
▼Twitter @wakayuka18 毎朝つぶやいています♪
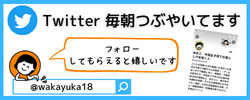
毎朝つぶやいてます♪
フォローしていただけると
嬉しいです\(^o^)/
***
当ブログはリンクフリーです。
「いいな♪」と思う記事がありましたらブログやSNSでご紹介していただけると嬉しいです。(許可や連絡は不要です)


