過干渉な親のセルフチェックリスト(小・中・高校生別)過保護との違いや親の心理
・子どもに毒親だ!と言われた
・どんな行動が過干渉になるのか?自分でチェックしてみたい
・過保護と過干渉の違いを知りたい
という方に、小学生高学年・中学生・高校生の3段階に分けて、ついつい親はやってしまいがちだけど、実は過干渉になる超具体的な事柄をリスト化しました。
親が子どもに「何かしてあげたい」「つらい思いをさせたくない」と思うのはいたって自然なこと。
ですが、それが度を超すと“過保護”や“過干渉”になってしまいます。
過去の私は、心配症が災いし過干渉な親になってしまったちょっと毒母。
言わなくていいことを毎日ガミガミ言っていて、子どもの生きる力をうまく育てられない状態でした、、、(涙)
そんな私が中高生ママ専門の子育てコーチとなり、4,000時間以上、悩めるお母さん達のお話を聴いてきました。
チェックリストとしてはちょっと細かすぎるかもしれませんが、自らを省みて過干渉な親を卒業!わが子の「生きる力」を育てたいと考える親御さんに読んでいただきたいです。

子どもの上空を飛び回り
常に子どものことを見張っていて
何かあれば手を貸しに
ぴゅーっと降りてくる親のこと
もくじ
過干渉と過保護の違い
過保護と過干渉の違いを調べてみると(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia))
過保護とは「子どもが望んでいることをやってあげすぎること」
過干渉とは「子どもが望んでいないことをやりすぎること」だとわかりました。
過保護の具体例は、(良かれと思って)鞄からお弁当箱や体操服を出して洗ってあげる、塾や学校への送り迎えなど。
子どもが困る前に親が先回りしてやるので、親子関係は比較的良いのが特徴ですが、自分のアタマで考えて動く力が育たず、共依存関係になりやすいです。
過干渉の具体例は、(良かれと思って)勉強や受験のことに口を出す、スマホをチェックしているなど。
子どもが望んでいないことにイチイチ口を出すので、親子関係が悪いのが特徴です。
どちらも「やってあげ過ぎること」が問題です!
混同されやすい「過干渉」と「過保護」ですが、特に過干渉は「子どもが望んでいないこと」を、やり過ぎてしまうことから、近年「毒」とみなされ、「毒親」の特徴としてあげられています。
▼参考記事▼
⇒過保護な親の特徴と甘やかされて育った子の行く末
⇒【過干渉に育てられた人の9つの特徴】毒親予備軍のタイプや口癖を解説
過干渉チェックリスト【小学生高学年】
ここからは、親子間にある境界線を踏み越えて、親がついついやりがちな過干渉な行動をリストアップしました。

チェックが付く項目は過干渉です。
今良かれと思ってやっている事をやらないようにすると→子どもの自主性や主体性が育ち、中学生以降の子育てが楽になります
- 子どもの宿題(自由研究や作文)に親が手を貸している
- 子どもの友人関係に口出しして、友達を選ばせている
- 子どもが困らないように先回りして、周りの人(学校や塾の先生、ママ友)にお願いして手を打っている(例:クラス分け)
- 子どもがやりたがらないこと(英語や武道など)を「このままでは将来困るから」とやらせている
- 忘れ物に気づいたら学校に届けている
- 忘れ物がないか毎朝親がチェックしている
- 子どもが宿題やプリントを持ち帰るのを忘れた場合、ママ友にお願いして写メを送ってもらうのが日常化している
- 習い事において、親の期待に応えないこと(やればできるのに頑張らないこと)にいら立っている
- 中学受験する場合、本人よりも親の方が一生懸命になっている
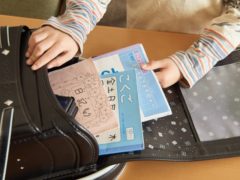
親はなるべく手を出さないで、見守る勇気を!
小学生過干渉チェック解説
毎日ちゃんと食べさせて、忘れ物のないよう学校に送り出したり、日々のサポートに一生懸命なのが小学生の親世代です。
特に、サッカーや野球、武道をさせている場合は、コーチや監督の采配に腹を立てていたり、わが子のやる気のなさに悩んでいたりと、子どもよりも親の方が一生懸命になっている場合も多くみられます(お父さんが指導している場合も多い)。
今一度、「そのスポーツをやるのは誰か?」を考えて、親は一歩引いたサポートができるといいですね。
また、小学生高学年くらいからは、「自主性を育てる」ことを考えて子育てできるとこの先ラクです。
そのためにも、よく気が付くタイプのお母さんは、先回りの育児をやめ、失敗させる機会を奪わないことが大事です。
過干渉チェックリスト【中学生】

中学生の反抗期は過干渉を辞めるチャンス!
親としての在り方を自問して修正!自主性や主体性が育つと、高校生以降の子育てが断然!楽になります!
- (頼まれていないのに)毎朝起こしていて、なかなか起きない子どもに困っている
- 夜寝る時間に文句を言っている(毎日「早く寝なさい」の声かけ)
- 学校や塾の送り迎えをしている(行かなくなったら困る気持ちがある)
- 子どもとの会話の半分以上が勉強や受験の話になっている
- 志望校や滑り止め校を親が決めている
- 毎回のテスト範囲が気になり、子どもの苦手な教科や単元について悩んでいる
- 友人関係や部活関係のことに「こうしたら?」などアドバイスしている
- 子どもの鞄を勝手に開けている
- 子ども部屋を勝手に片づけている
- 苦手克服のためになりそうな問題集を(良かれと思って)勝手に買っている
- 勉強のやり方に口出しをしている
- 自作のプリントを作るなどして、勉強を手伝っている
- ゲームの時間や場所のルールをつくり、厳しく管理している

中学生過干渉チェック解説
中学生は塾世代。
塾の送り迎えしている方が多いですが、無理に行かせていることも多く、イライラ育児の要因になっていることもあります。
また、子どもが朝起きないことに悩んでいる人が多いのも、中学生の特徴です!
朝起きることについて、どんなサポートが欲しいと思っているのか?(もしくはいらないのか?)親子で一度ゆっくり話し合ってみるといいですね。
反抗期や高校受験もあって、難しい時期にはなりますが、自分の不安を解消させようとする「先回りの育児」を、高校生まで持ち越さないようにしましょう。
▼中学生ママに▼
⇒勉強しない中学生は基本ほっとく?ほっといてもうまくいく7つの方法
過干渉チェックリスト【高校生】

「うちの子は高校生になっても、自分から何もしようとしない…」という不満をお持ちの方は、これまでの過干渉な育児が悪影響になっている可能性大です。今からでも遅くないので、子どもが10代のうちに過干渉から卒業できますように。
- 友達付き合いや約束事(待ち合わせ場所・時間や持ち物など)に口出ししている
- 着る服に文句を言う。又は親が着せたい服を着せている
- お金の使い方について文句を言ったり、報告させている
- 友達同士の旅行の際(頼まれていないのに)予約したり、送り迎えをしたりしている
- 子どものことを優先しすぎて(例:送り迎えや勉強のサポート)、自分の人生を楽しめていない
- (頼まれていないのに)試験勉強の時間管理や資料集めをしている
- 大学のオープンキャンパスの段取りをし(本人は行きたくないのに)何とかして連れていこうとする
- (頼まれていないのに)大学や予備校の資料請求を母がしている
- 子どもからラインをブロックされたり、未読(既読)スルーされている
- (心配なので)子どものラインやメールなどを見ている
- GPSで子どもの居場所を常に確認している
- 勉強以外に時間を使うのはもったいないので、勉強以外のことはなるべく代わりにやってあげている
- 子どもの交友関係やスケジュールなどを把握していないと不安で仕方がない

お互いが必要以上に依存しあう
親子関係にご注意を(例マザコン)
▼関連記事▼
息子をマザコンにする母の特徴~毒親脱出法~
高校生過干渉チェック解説
高校生は子育ての最終段階。
まだいろいろと危なっかしいかもしれませんが、親として子どもを一人の大人として尊重して扱うと、グググーンと成長する時期でもあります。
勉強のことはもちろん!服装や友人関係などについても、手出し口出ししたいのをグッと我慢して、自由を与えてあげませんか?
行動を監視して「見張っている子育て」が日常化すると、親離れも子離れもできなくなります。
高校生の子育てにおいて、現在「わたし過干渉かも」と感じた方は「笑顔で自立していく子」を育てるには自分の何を変えればいいか?という「問い」を常に心においてくださいね。
「笑顔の自立」!まだ間に合います。
▼高校生ママに▼
⇒勉強しない高校生のトリセツ~やる気を出すために必要な3つのこと~
過保護や過干渉になる親の心理
私達親は、どうして過保護や過干渉になってしまうのでしょうか?
それぞれの心理についてお伝えします。
過保護になる親の心理
過保護は特に心配性でよく気が付くタイプの親がなりやすいです。
先回りして、子どもの失敗や挫折を取り除いてあげることで、悲しむ姿を見ずに済み、自分も(失敗するわが子の姿を見て)苦痛を感じなくて済むというメリットがある為に習慣化しやすいのです。
また、親御さん自身が自分の親から過保護に育てられてきたために、子どもへの過保護な接し方が“当たり前”だと認識しているケースもあります。(過保護の連鎖)
わが子は大切な存在だからこそ、過剰に保護してしまいやすいんですよね。。。
過干渉になる親の心理
過保護と違って、過干渉は(子どもの望むことではなく)親の望むことを子どもに強いるため、子どもの気持ちが全く無視されている点が特徴です。
ですので、親子仲が悪くなります。
親は、良かれと思って(ただし全く悪気はない)子どもの問題に介入し、自分が問題解決しようとしてしまっています。
例えば、受験の際、「この子は自分から頑張るタイプの子ではないから、公立高校よりも面倒見のよい私立高校が方がいい」と親が先回りして誘導していたり、子どもが自分の気持ち(例:友達と同じ高校に行きたい)を話していたとしても「そんな理由じゃダメ、自分のことなのに、一体何考えてるの!」と子どもの言い分を聞き入れない、みたいなことが日本の多くのご家庭で起きています。
子どもを思い通りに操りたいというコントロール欲求(支配欲)が働いているのです。

自分の感情をコントロールできない人は、子どもをコントロールしようとしてしまいやすいです!(過去の私です)
過保護や過干渉が子どもに与える4つの悪影響
では、過保護や過干渉な子育てをしてしまうと、育てられる側の子どもにどんな悪影響があるのでしょうか?
ここでは4つご紹介します。
- 自分に自信がなくなる(自己肯定感が低くなる)
親が子どもに介入しすぎることは、子どもの自尊心が育たなくなる可能性があります。
というのは、子どもは失敗を乗り越えていく過程で、少しずつ自信をつけていくからです。
過保護な親は、親が先回りして失敗しそうな要因を取り除いてしまいますので(カーリングペアレント)、そもそも失敗経験が少なく失敗を乗り越えた経験も圧倒的に少なくなるために、自分に自信が持てなくなってしまいます。
また、過干渉な親の子どもは、自分の意見を否定される環境で育ちます。
当然、自分に自信を持つことが困難になりますので、自己肯定感の低い大人へと成長するというわけです。 - 自己主張できなくなる
過保護や過干渉な親の元に育つと、自分が声をあげなくても、代わりに親が他人と交渉してくれることに慣れてしまいます。
親が代弁してしまうために、「自分の気持ち」を人前で主張する必要がなくなるという訳です。
つまり、自己主張をする能力が弱くなってしまうんですよね、、、
ですので、例えば嫌なことをされても「やめて」と言えなかったり、どう対応して良いかが分からなくなっていってしまうのです、、、(大問題) - 他人への思いやりが育たない
過保護な親に育てられると、子どもはいつでも“自分が一番”と考えてしまいがち。
他人を顧みる必要がないため、ジャイアンのように自己中で、思いやりのない子に育ってしまう可能性があります。
また、過干渉な親に育てられると自分の気持ちを否定されるため、自分のことを大切な存在だと思えなくなってしまいます。
自分を大切に思えないと、他人を大切にする気持ちも芽生えません。 - 自主性や主体性が育たない
自主性とは、自主的に行動しようとする性質のこと。
主体性とは「自分のアタマで考えて動く力」のことで、「みんなと同じ」ことに安心感を感じやすい日本では、この主体性のある人は貴重だと言われています。
ですが、過保護な親の下で育つと、子どもが自分で考える前に、親が動いて安全なレールを敷いてしまうので、この主体性は育ちません。
また、過干渉な親の下では、否定ばかりされるために自分を肯定する力が弱くなり、例え、何かやりたいことが頭に浮かんだとしても「どうせ自分には無理だ」とやる前に諦めてしまうことが多くなります、、、

過保護や過干渉が子どもに与える悪影響はめっちゃデカいです!!
今を乗り切る事(例:直近の受験)を優先している方が多いですが、10年後20年後まで視野を広げて、大切な大切な「生きる力」を育ててまいりましょう。
過干渉な親にならないために、今日から出来る3つのこと
子どもが自信を携えて!笑顔で自立していくためにも、過干渉な親は卒業したいですよね!
過去、過干渉な親だったと自覚している私自身が、実践することで効果があった方法を3つご紹介します。
- 比較しない
華やかなママ友と、パッとしない自分。
優秀なあの子と、やればできるのにちっともやる気を出さないわが子。
誰かと比較していると、子どもをコントロールしたくなって過干渉になってしまいます。
比較するのをやめて、自分やわが子の「ありのままの姿」を受容できるようになると、私はとってもラクになりました。 - 自分の不安を子どもに解消してもらおうと思わない
「このままでは(世間体のいい)大学に入れなくて、子育て失敗したと笑われるかもしれない」という不安から、過干渉なちょっと毒母になってしまっていた私(涙)
自分の不安を、子どもに解消してもらおうとしていました、、、(←コレ子どもに依存している状態)
ですが、この状態にある自分に気づいたことで、子どもの問題(受験や勉強)と、自分の問題(母としての不安)を分けて考えられるようになり、自分の不安は自分で解消できる自分へと舵取りしました。 - 子どもの力を信じて見守る
自分の課題を解決するには、心にエネルギーが必要ですよね。
ストレスフルで余力がない状態では、よしやろう!やってみよう!という気持ちにはなりにくいからです。
うちの子には「自分で何とかする力」があると信じて見守ることが、子どもの力(エネルギー源)になります。
信じて、任せて、見守って。
愛情エネルギーをたっぷり注げる親になれますように。
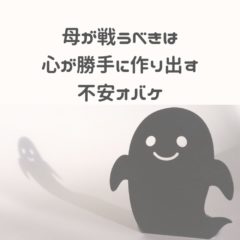
自分のご機嫌を自分でとれる人に☆
▼(PR)勉強しない!ゲームばっかり!にお悩みママに
\どちらも無料/
❶メール(文字)で学びたい方に⇒7日間メールセミナー(登録無料)
❷(New!)動画で学びたい方に⇒7日間【動画】セミナー(登録無料)
この記事を書いた人(監修者)
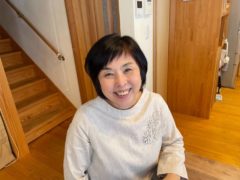
長野県松本市在住
中高生ママ専門の子育てコーチとして、悩める母専門のコーチングセッションを行う。
【経歴】
・コーチングオフィス ままはぐ代表
・ICA国際コーチ協会認定 ポテンシャルコーチ
・セッショントータル4,500時間以上を実施
・24歳(社会人)と21歳(大4)2人の息子を持つ母親
・京都大学にて教授秘書歴7年
New! オンラインサロン「母テラス」

月額3900円で
ブレない子育て軸を手に入れませんか?
2024年1月~「見守る子育て」のオンラインサロンができました\(^o^)/
❶月替りで有料動画 ❷個別サポート先行案内 ❸ランチ会も! ❹LINEでカンタン♪ ❺匿名で参加できる ❻コツコツ行動→なりたい自分に速やかに成長❼zoomセミナー(お悩み回答室)など。
動画で学べて(インプット)、チャット欄で毎日アウトプットできるから、1日でも早く!「見守る母」になりたい方に超オススメ。
子育てこんなに頑張っているのに!!どうしても毒を吐きたい時は「毒吐き→浄化ルーム」へどうぞ。
3日くらいしたら私がそっと「早く笑顔になりますように☆」という気持ちを込めて、その投稿をそっと消去しています。(始まってすぐに人気のお部屋になっています)
お知らせ
ただいま、わかばやしが直接サポートするコースは満席になっており、お申込みをストップしています。
空きが出ましたらライン@やメルマガにてお知らせさせていただきます。(2023年2月中旬に3月生さんを若干名、募集予定です)
\登録無料/
▼ライン公式アカウント(←週3でブログ更新のご案内があなたのスマホに届きます♪)

週3回の配信
▼7日間無料メールセミナー(←こじらせていた私自身の話)
毎週(月)朝に配信
▼YouTube わかばやしゆかこ「見守る子育て塾」週2更新♪
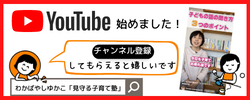
YouTube週2回更新♪
チャンネル登録していただけると
嬉しいです~~
▼Twitter @wakayuka18 毎朝つぶやいています♪
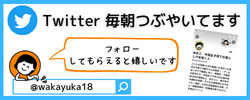
毎朝つぶやいてます♪
フォローしていただけると
嬉しいです\(^o^)/
***
当ブログはリンクフリーです。
「いいな♪」と思う記事がありましたらブログやSNSでご紹介していただけると嬉しいです。(許可や連絡は不要です)



おはようございます
LINEやブログを読ませていただいてます、
読めば読むほど、自分にあてはまることばかりです。
誰かのために何かをしてあげる、人の役に立ちたい
、世話好き、自分の幸せより子供達の幸せ、自分ののことより子供達のこと優先
それが自分のやるべきことと
心の底から思っていました。
人の役に立つことで自分もやった感が満たされて、それは自分の存在意義を求めていたのかもしれません。
私自身三姉妹の長女で、しっかり者で、頭もよく、美人で、スタイルもよくて‥と母に言われて育ちましたが、
まさに条件付きだったのかなぁと思いました。
ブログを読んで、
あなたのままでいい
今のままでいい
生きてるだけで幸せ
笑顔でおはよう、おやすみなさい
私は無意識に
高2の息子、中2の娘、小6の娘いますが、
末娘には常にそうしていましたし、そう思っています。そして、末娘はなんでも頑張れる、生きるパワー、自分でやる力があります。
そして、息子には
産まれた時から
ずーっと心配で、心配で、心配で、手取り足取り、まさに先回りの育児をしてきたことに気付かされました。
仕事も接客業でした、更に私の気づきのアンテナは磨かれてしまいました。
人のお世話が大好きな私は
可愛い分身に全てを注いでしまいました。
転ばないように、嫌な思いを少しでもしないように、
それが息子の幸せに繋がると信じていました。
小学生、中学生の過干渉チェックやりましたが‥過干渉そのものです。
共依存も
まさに私と息子の関係です。
自分は勉強することで、人生がいい方向に向かったと信じていたので、
そのよき道を息子にもと、
勉強頑張ってほしい思いにとらわれてました。
それが息子の幸せと信じてました。
恐ろしいですね。
私は怒りの感情やカッとなることはあまりないので、息子は自己肯定感は低くないと思っていましたが、いつも息子のことを心配し、息子の将来を不安に思っていました、そういう不安視が自己肯定感を低くしてることも今回知りました。
私自身、急激に変われるか分かりません。でも
変わっていきたいです。
ありがとうございます。
気付きを教えてくれて、涙涙で読んでいます。
ありがとうございます
キッキーさま
コメントをありがとうございます。
私の言葉がキッキーさんの心に届いたことを教えていただいて、こちらこそ感謝する気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございます。
自分で気づくことができるキッキーさんならきっと大丈夫です(*^_^*)
応援しています(^^)/
私自身、教育ママでしたので黒歴史が満載の人生でしたが(母としての前半の人生)、そんな私を許してくれた息子達。