【子どもの自主性を育てる方法7選】主体性との違い、求められる理由、NG対応
・受験も朝起きることも。全部自分のことなのに、自主的に動こうとしない子どもが心配
・自分から自主的に動く子の育て方が知りたい!
こういった方に。
今の日本では、先回りして、子ども本人に考える時間を与えずに「早く早く!」と急かしてしまっているために、自分で考えて動く力が育っていない子(大人)が多いと感じています。
今日は「子どもの自主性」を育てる方法9つとNG対応を徹底解説いたします。
特に、思春期・反抗期を迎える中高生の子育てにおいて、わが子の自主性を育てることを見据えていると、その子が自立を迎える〇年後には親がうるさく言わなくても自分で考えて動く子になっていますのでオススメです。(私は今めっちゃラクです~)
子育てコーチングをベースにした「見守る子育て」では、自主的に動き始めたお子さんのご報告を沢山いただいております。

自主性は、口うるさい親の下では育ちません。
もくじ
自主性と主体性の違い。まずは自主性を育てよう♪

「自主性」とは、誰かからの指示がなくてもやるべきことを率先しておこなう性質のことです。
なので、「自主性のある子」とは、やるべきことを自分からやる子。
例えるならば、親が何も言わなくても自分から進んで宿題をやる子といった感じ。
「自主性」と似ている言葉として「主体性」があります。
「主体性」とは、どんな状況においても「自分の意志」や「判断」で責任を持って行動する態度や性質のこと。
なので、「主体性のある子」とは、どうすればいいかを自分で考えて責任をもって行動する子。
例えるならば、受験前、何をどれだけ、どんなふうにやると合格できるかを、自分で考えて行動に移す子といった感じでしょうか。
日本人は「皆さんそうしてますよ」で行動を起こす人が多いと言われていますので、この「主体性」を持っている人はすごー--く貴重な人材です。
「自主性」と「主体性」の違いは、「自分の頭で考えるかどうか」があるかないか。
私は、子育てコーチとして、最終的には「主体性」を持って生きる子がどんどん増えてほしいと思っていますが、まずはその第一歩として、子どもの「自主性」を育てようとする親御さんが増えてほしいと考えています。
▼主体性のある子を育てる方法はコチラ▼
⇒主体性がない人の特徴と原因。就活で困らない子を育てる方法
今!自主性が求められる理由
最近(2023年)登場し、大きな話題となっているChat GPTをご存じでしょうか?
これは、米 OPEN AI社が開発した “AI(人工知能)を使ったチャットボット” で、テキストメッセージを入力すると、それに応じた答えを返してくれるAIです。
簡単な質問だけではなく、文章の要約や、小説や詩の創作、英文の翻訳など、さまざまなことに使えます。
このChat GPTをはじめとして、無人レジ・お掃除ロボット・自動運転車などが登場し、AIが身近になった現代では、多くの人間の仕事は消えていくとも言われています。
実は、10年前に私がコーチングを学んだ時にも「10年後なくなる仕事」についてよく話題に上がっていましたが、コロナ禍ではこれが一気に加速した印象があります。
こういった変化を目の当たりにして、「ロボットに負けない力=自主性や主体性」が育っていないと、例え高い学歴を持っていたとしても困る時代がやってくると感じています。

「(〇大卒なのに)使えない人」「言われたことしかしない人」って、私たちの周りにもいると思いませんか?
子どもの自主性を育てる方法7選
では、やるべきことを自分からやるという「子どもの自主性」はどうしたら育つのでしょうか?
コーチングは人を育てるのが得意な手法ですので、今日は毎日の育児で使える方法を7つご紹介します。
どうぞ、自分のお子さんのコーチになることをイメージしながら読んでみて下さいね。

仕組みをつくってしまえば
ラクチンです
1)自分で考えさせる習慣
コーチングは質問が特徴的なコミュニケーションスキルです。
ですので、「あなたはどうしたいの?」「どうしてそう思ったの?」などの質問を使って、子ども自身が自分で考える習慣をつくっていきましょう。
2)余計な口出し・アドバイスをしない
何かを始める前に「こうしたら?」「あれは?」などのアドバイスや提案もNGです。
例えば、「自由研究は〇〇にしたら?」「面接の時は〇〇について話すといいよ」など、アドバイスばかりしていると、ゼロから考える力(着想)が育ちません。
「そうはいっても、ほっておいたら本当に何もしないから、、、」とおっしゃる親御さんは多いと思いますが、実は、我慢できずに先回りして良かれと思う提案をしてしまうからこそ、余計に自分で考えなくなるという悪循環を引き起こしているのです、、、
誘導しないこと、ゼロから考えさせることを意識するといいですね♪

あなたはどうしたいの?
どんなアイデアがある?(ゆっくり考えたらよいよ~)
3)指導者よりも理解者で
子どもより上にいる指導者型の親御さんが多いと感じていますが、思春期以降は理解者になることを意識すると良いですね。
なぜなら、親が指導ばかりしていると、自分で考えようとしなくなるからです。
例えば
あなたが会社に入ったばかりの新入社員だったとして、配属された部署に、常に部下に上から目線なA上司と、えらそぶらずに部下の気持ちを理解しようとしてくれるB上司がいたとします。
AとB、どちらの上司が自主性を伸ばせそうだと感じますか?
私は断然!B上司です。
人の気持ちを理解しようとする上司の下では、まだ新人だったとしても、自分の意見を恐れず話せそうで、社会人としてもどんどん成長していけそうな感じがするからです。
B上司の周りには、自然と意欲的な社員が集まり、どんどん有能な社員が沢山育つことでしょう。
いま子どものダメな部分を修正しようとしてよき指導者(管理者)になろうとしている親御さんが多いですが、我が子の「よき理解者」になることを心がけましょう。

今興味あることは何?
きっと貴方ならできると思うよ
4)良い聞き手になる
言葉かけ(働きかけ)を探している方がほんとー--に多いですが(めっちゃ質問されます!コントロール欲がある証拠だと)、それよりも何よりも受け身の対応「良い聞き手になること」を目指すのがいいですね。
というのは、人は自分の話を聞いてほしい生き物で、良い聞き手がいると沢山自分のことが話せるからです。
そして、自分の気持ちが整理されたり、やりたいことが明確になったりします。
また、話しているうちに「もっとやってみよう」という意欲がわいたりすることも多いのです。
ちなみに、人の話を聞く時のポイントは、相手が7割で自分が3割。
お子さんの自主性を育てたいお母さんは、この比率を意識してみてくださいね。

子どもに沢山語らせてあげて下さいね。
ちなみに今は1:9くらいで
質問責め。
何でも知りたい母が多い、、、
5)否定しない(肯定的な関わり)
そのつもりはなくても「でも」や「ただ」などと言う言葉で、子どもの気持ちをバッサリ否定している親御さんは非常に多いです。(ご本人は無意識。個別サポートコース中にフィードバックすること多し)
何を言っても『否定されない安心感』を創ってあげませんか?
子どもにとって家が安心できる居場所になると、自由に自分の気持ち(意見)を話せて「よし、やろう!やってみよう!」という気持ちにもなりやすく、自主性も伸びやすいです。
6)失敗を恐れない
子どもが失敗することを恐れる親御さんは非常ー--に多いです。
これは、子どもの評価が自分の評価に繋がっているように感じるためだと思います。
ですが、失敗は、すればするほど、優しく、強く、人間力を高めてくれるものだと、それこそ失敗を沢山してきた私は感じています。
定期テストでの失敗をはじめ、赤点や留年、不登校、不合格など、ネガティブな面だけを見て恐れていると、叱咤激励が多くなり子どもの自主性を伸ばすことができません。
別の捉え方が出来る人に。視野の広い親を目指していただきたいです。
7)信じて任せる
人育てが上手な人は、やり方に口を出さない人。(イメージとしては、お金だけ出してうるさく言わないスポンサー的な立ち位置)
私は、「やってみなはれ」(サントリーグループ創業者・鳥井信治郎さんの言葉)という言葉がすごく好きで、子育てに迷った時は思い出すようにしています。

「やってみなはれ。責任は私がとるから」
↑こんなカッコいい言葉を言える母親でいたいです~
▼子育てコーチングを詳しく知りたい方に▼
⇒子育てコーチングとは?自主性を引き出す3つの方法(資格がなくてもすぐに実践できます)
子どもの自主性が育たない!親のNG対応3つ
自主性が育たなくなる親のNG対応を3つご紹介します。
1)過干渉
自主性が育たたないNG対応の筆頭は「過干渉」です。
過干渉とは、子どもが望んでいないことを、親がやりすぎてしまうことで、毒親の特徴。
自主性を育てるどころか、やる気の芽をつぶしてしまったり、無気力な子に育ってしまったりします。
例えば
中学生では
・朝起きる時間や寝る時間
・部活のこと
・勉強のやり方
・塾へ行く行かない
・ゲームの時間管理
・志望高校の選定
高校生では
・友達付き合い(彼氏や彼女との付き合いも含む)
・生活態度
・バイトのこと
・部活のこと
・勉強のやり方
・ゲームや動画の時間管理
・受験大学の選定
などにおいて、自分の価値観を押し付けるお母さんやお父さんが多くみられ、子どもの自主性を育てられずにいます。
▼過干渉かを知りたい方向け記事▼
⇒過干渉な親チェックリストどこからが毒親?
2)過保護
「過保護」とは、子どもの望んでいることを親がやり過ぎてしまうことですが、よく気が付く心配性のお母さんに多いのが、本人の望み以上に多めに段取りしてしまうことです。
基本、子どもがかわいそうだからと、いろんなことで「困らないように」いつも少し多めにカバーしてお膳立てしてあげているために、先回りの育児をして子どもが自分で考える機会を奪ってしまっているのです。
例えば
・「ノートがないから買っておいて」と子どもに頼まれたら、ノート以外にもシャーペンや消しゴムも買ってあげる
・塾の送り迎えするのが当たり前になっていて(自転車でも通える距離)、「行き」は時間に遅れたら駄目だから、「帰り」は寒くてかわいそうだからという過保護な理由で迎えに行っちゃう。

子どもに何か頼まれたら、ぴったりの分量か、もしくは少し足りないくらいのサポートを心がけてみるといいですね。
3)重箱の隅をつつく子育て
宿題や持ち物など、子どもがちゃんとしているか?をイチイチ確認作業をしている母は多く、これでは子どもの自主性は育ちません。
子どもは痛い目に合って初めて、自分の行動を変えようという意識が芽生えます。
「宿題したの?」「忘れ物ない?」「本当に大丈夫?」などが口癖になっている方は修正しましょう。
自主性が育たたないと将来どうなる?
では自主性が育たないと、子どもは将来どうなってしまうのでしょうか?
ここでは8つ挙げてみます。
- 親の顔色を伺う
- 自分で決められない
- 人のせいにする
- 愚痴や文句が多い(被害者意識・他責)
- 打たれ弱くなる
- 指示待ち族で一生誰かに従う人生
- チャレンジしない人生
- 自分らしく生きられない(生きづらさ)
また、前述したように、誰でもできる仕事は、正確性や速さにおいてロボットに負けてしまうので、経済的に困る未来が来てしまうかもしれません。
▼参考記事▼
⇒【過干渉に育てられた人の9つの特徴】毒親予備軍のタイプや口癖を解説
⇒過保護な親の特徴と甘やかされて育った子の行く末
子どもの自主性を育てたい親御さんに
コロナ禍の日本では「2極化がさらに加速する(富裕層と貧困層)」と言われています。
この2極化を分けるカギとなるのが、私は、自主性や主体性ではないか?と感じています。
また、教育面では、2021年より大学入試において、約30年続いた「センター試験」は廃止され、新たに「大学入学共通テスト」となり「思考力・判断力・表現力」を一層重視するカタチに変わりました。
この流れを見ると、これからの日本では、自分の頭で考え、自分で判断し、自分らしく表現できる人材が、より必要とされ、重要視されることが考えられます。
将来は、経済的に苦労してほしくない!
我が子には幸せになって欲しい!
と願うのが親と言う生き物ですが、目先の学歴のために、親や先生など、大人が細かく管理する体制では「自主性」という大切なものが育ちません。
どうぞ、子どもの「よき理解者」となっていただき「信じて見守る」親御さんが増えますますように☆
▼(PR)勉強しない!ゲームばっかり!にお悩みママに
\どちらも無料/
❶メール(文字)で学びたい方に⇒7日間メールセミナー(登録無料)
❷(New!)動画で学びたい方に⇒7日間【動画】セミナー(登録無料)
この記事を書いた人(監修者)
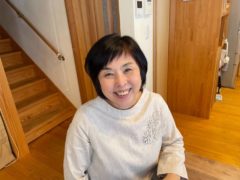
長野県松本市在住
中高生ママ専門の子育てコーチとして、悩める母専門のコーチングセッションを行う。
【経歴】
・コーチングオフィス ままはぐ代表
・ICA国際コーチ協会認定 ポテンシャルコーチ
・セッショントータル4,500時間以上を実施
・24歳(社会人)と21歳(大4)2人の息子を持つ母親
・京都大学にて教授秘書歴7年
New! オンラインサロン「母テラス」

月額3900円で
ブレない子育て軸を手に入れませんか?
2024年1月~「見守る子育て」のオンラインサロンができました\(^o^)/
❶月替りで有料動画 ❷個別サポート先行案内 ❸ランチ会も! ❹LINEでカンタン♪ ❺匿名で参加できる ❻コツコツ行動→なりたい自分に速やかに成長❼zoomセミナー(お悩み回答室)など。
動画で学べて(インプット)、チャット欄で毎日アウトプットできるから、1日でも早く!「見守る母」になりたい方に超オススメ。
子育てこんなに頑張っているのに!!どうしても毒を吐きたい時は「毒吐き→浄化ルーム」へどうぞ。
3日くらいしたら私がそっと「早く笑顔になりますように☆」という気持ちを込めて、その投稿をそっと消去しています。(始まってすぐに人気のお部屋になっています)
お知らせ
ただいま、わかばやしが直接サポートするコースは満席になっており、お申込みをストップしています。
空きが出ましたらライン@やメルマガにてお知らせさせていただきます。(2023年2月中旬に3月生さんを若干名、募集予定です)
\登録無料/
▼ライン公式アカウント(←週3でブログ更新のご案内があなたのスマホに届きます♪)

週3回の配信
▼7日間無料メールセミナー(←こじらせていた私自身の話)
毎週(月)朝に配信
▼YouTube わかばやしゆかこ「見守る子育て塾」週2更新♪
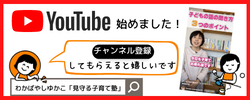
YouTube週2回更新♪
チャンネル登録していただけると
嬉しいです~~
▼Twitter @wakayuka18 毎朝つぶやいています♪
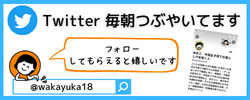
毎朝つぶやいてます♪
フォローしていただけると
嬉しいです\(^o^)/
***
当ブログはリンクフリーです。
「いいな♪」と思う記事がありましたらブログやSNSでご紹介していただけると嬉しいです。(許可や連絡は不要です)


